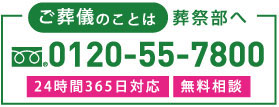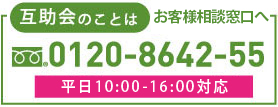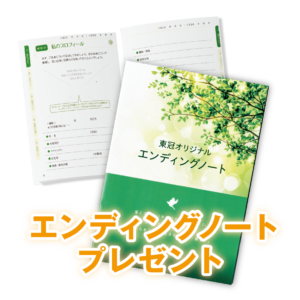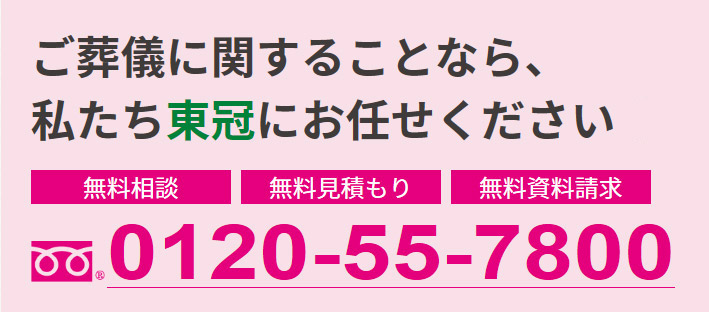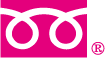身近な方が亡くなった際、とくに亡くなった方が親族の方の場合、赤ちゃんも一緒に連れて行き故人様ときちんとお別れをしたいものです。
ですが、「ご葬儀の途中で泣いてしまったら、おしめの交換、授乳などどうすれば?」「そもそも赤ちゃんを連れていくことが非常識にならないの?」と不安な方も多いようです。
今回のコラムでは、赤ちゃんと一緒にご葬儀に参列する際のマナーや注意点、ポイントについてご紹介していきます。
そもそもご葬儀に赤ちゃんを連れていくのは良くない?!
葬儀は故人様を静かに見送る場です。参列者はみな厳粛な気持ちで式に参加しているでしょう。でも赤ちゃんはちょっとしたことで泣き出すものです。赤ちゃんが泣くのは仕方がないこととはいえ、葬儀の最中に騒がしくされることを嫌がる方も多いでしょう。
赤ちゃんの泣き方には個人差があり、月齢によっても違います。1歳近くなり、元気な赤ちゃんならかなりの大声でなくケースもあります。「故人様とお別れしたくて無理して参加したが、厳粛な雰囲気を壊してしまった」と後悔する場合もあるでしょう。
しかし、故人様が身内である場合は、最後のお別れということもあり赤ちゃんを連れて行きたい方もいると思います。とくに故人様が「会いたがっていた」「赤ちゃんを可愛がっていた」ということであれば、赤ちゃんと一緒に参列した方が故人様もきっと喜ぶことでしょう。
まずは遺族・親族に相談をしてみましょう。ご遺族様や親族が了承すれば、赤ちゃんを連れて行ってかまいません。反対に、「お気持ちだけで」とやんわりと辞退を求められたら、参列は控えましょう。葬儀に参列できなくても、弔電やお供物、花を送るなど弔意を示す方法はいろいろあります。
また、後日お宅へお邪魔して、お線香を上げさせてもらってもよいでしょう。
赤ちゃん連れで葬儀に参列することになったら?
現在は、授乳室やベビーベッドなど赤ちゃんをお世話する設備が整っている式場も多いです。その一方で、家族葬用の小さなセレモニーホールには、十分な設備が整っていない所もあります。近年はホームページでセレモニーホールの中を公開しているところもあるので、事前に確認しておきましょう。万が一のときに備えて、近所のドラッグストアやコンビニの一をチェックしておくと安心です。
赤ちゃんと参列をする場合、ご葬儀が始まる前にご遺族にご挨拶をし、すぐに動けるよう後ろの席・出入口付近に席を確保しましょう。
葬儀社の方に言っていただければ手筈を整えてくれるはずです。
赤ちゃんは何か月から葬儀に参加できる?
赤ちゃんは、元気ならば基本的に何か月からでも葬儀に参列できます。ただし、産後すぐの場合、赤ちゃんは元気でもお母さんに出産のダメージが残っているケースもあります。安産で立ち振る舞いに問題がないなら大丈夫ですが、医師から安静にするように指示が出ている場合は無理をしてはいけません。
月齢が高くなると、人見知りをするようになる一方、眠る時間がある程度決まってきます。お昼寝時間が近くになったら激しく泣き出すこともあるので、お葬式の時間がお昼寝の時間に近い場合は、寝かしつけてからそっと会場に入るなど工夫しましょう。また、月齢が高い場合は託児サービスなども利用できるようになります。
赤ちゃんと一緒のご葬儀で役立つアイテムの使い方・マナー

始終抱っこ紐でというのは大変なものです。ベビーカーをお葬式会場に持ち込んでも問題ありませんので、持参されると良いでしょう。ベビーカーの色を気にされる方もいますが、どんな色でも問題はありません。(買い替える必要はなく、参列者の方もご親族の方もあまり気にされません)
その他持って行きたいアイテムをまとめてみました。
赤ちゃんの服装はどんなものが最適?
赤ちゃんの服装は基本的には気にする必要はありませんが、あまりに派手な色合いや柄のものは避けましょう。シンプルなデザインでグレー・黒・紺色などのものが良いでしょう。
靴下に関して色は白でも大丈夫です。清潔でシンプルな靴下を履かせましょう。歩くことができる場合には、グレーか黒の靴下を、無ければ白色に。キャラクターものなどは避けると良いと思います。
祭儀場のホールの中には祭壇の花があるため、温度が低めに設定されていることも多いです。赤ちゃんの羽織れるものか、ひざ掛け、タオルやおくるみが一枚あると便利です。
赤ちゃんを大人しくさせておくには、おもちゃやおやつも効果的です。おやつを与える場合は静かに食べられて匂いの少ないものを選んでください。また、おもちゃも同様に音が出ないものを選びましょう。
動画を見せていると大人しい場合は、無音にしておきます。
あくまでも葬儀の場である、ということを忘れずに。
ベビーシッターを利用してみる
現在は、地域によっては当日でもベビーシッターを依頼できます。近しい方やお世話になった方が亡くなり、どうしても葬儀に出席したいが赤ちゃんがよく泣くなど参列がはばかられる場合は、ベビーシッターに葬儀の時間だけお世話を依頼してもいいでしょう。
また、葬儀社によってはベビーシッターを紹介してくれるところもあります。

席を立っても失礼・マナー違反にはなりません。スムーズに会場を行き来できるよう、最初から出入口付近や後ろの目立たない席を選んでおきたいですね。
赤ちゃんにとって、初めて会う人が多い、はじめての空間ということもあって落ち着か終始泣いてしまうケースもあるでしょう。そういった場合には、ご葬儀の間は控室で赤ちゃんと過ごして焼香の時だけお世話を変わってもらうという方法をする方がほとんどです。
頻繁に席を移動したり、赤ちゃんの泣き声が終始続いたりするようであれば、その方がママ・パパの気持ちも楽ですし、参列者もゆっくりと故人様とお別れができるでしょう。
赤ちゃんを理由に葬儀に出席できない場合の対処方法
故人様にはお世話になったけれど、どうしても赤ちゃん連れでは葬儀に出席できないといったケースもあります。ここでは、赤ちゃんを理由に葬儀に出席できない場合の弔意の表し方を紹介します。
香典を送る
葬儀に参列しなくても香典を送ることで弔意を表すことができます。香典は、代理人に持っていってもらうか郵送するかのどちらかにしましょう。代理人に持っていってもらう場合、自分の名前とともに、左下に「代」と書きます。配偶者に代理で出てもらう場合は、「内」を記しましょう。
香典を郵送する場合は、自宅に郵送する場合と斎場に郵送する場合があります。どちらがいいのかは、遺族に聞いておきましょう。斎場に郵送する場合は、斎場に事前に郵送可能かどうかを確かめておきます。
なお、郵送で送る場合はお悔やみの手紙を同封すると丁寧です。なお、香典を送る場合は必ず現金書留で送って下さい。現金書留以外の方法で送るとトラブルの原因となります。
弔電を送る
弔電は、ネットでも即依頼できるので赤ちゃんがいるご家庭でも便利です。NTTをはじめ複数のサービスがあり、当日申し込んでも配送してくれる所もあります。スタンダードな電報のほか、プリザーブドフラワー電報、西陣織電報、お線香付き電報など複数の種類があります。香典と併せて送るのもおすすめです。
お花やお供物
お花やお供物もインターネット経由で依頼できます。また、葬儀社経由で申し込むこともできます。お花やお供物は弔意を表す代表的な贈り物ですが、遺族が辞退している場合もあります。送る前に必ず遺族に確認してください。了承を得たら、他の供物やお花の値段に併せたものを送りましょう。
葬儀社によっては、自社のものしか受け付けないものもあります。事前に確認しておくとスムーズです。お供物は、お菓子や果物、日持ちする缶詰のほか、仏式ならば線香などもおすすめです。
弔問
葬儀やお通夜に参列できなくても、後日弔問に訪れて弔意を表すこともできます。弔問は遺族が了承したらいつでもいいですが、可能ならば四十九日までに行なうといいでしょう。赤ちゃんは預けられるなら預けると落ち着いて弔意を伝えられます。
弔問に訪れる場合は、手土産は不要ですが、葬儀時に香典を送れなかった場合はこのときに持参します。また、故人様が好きだった果物やお菓子などを持参してもいいでしょう。仏式で故人様の葬儀を行なった場合は、お線香もおすすめです。
なお、家族葬を行なった場合、弔問客が頻繁に訪れる場合もあります。そのようなときは長居をせず、お悔やみを述べて故人様に挨拶したら早めに辞去しましょう。逆に時間に余裕がある場合は、御遺族様と故人様についてゆっくり話をしてもかまいません。
まとめ
赤ちゃんと一緒にご葬儀に参列する際に抑えておきたいポイントなどご紹介してまいりました。
基本的には関係の深い遺族の場合でのみ、赤ちゃんと参列をすることになります。それ以外の場合は、故人様との関係性によると言えるでしょう。
赤ちゃんとの参列はとても大変なものです。その点は、他の参列者の方も理解をしてくれますので、「万全の準備を整えて参加する」と決めて、それでも上手くいかない場合は皆誰も非難をしませんから安心して故人様を供養されてください。