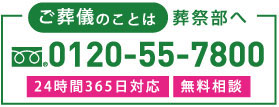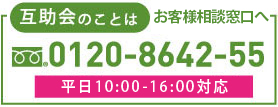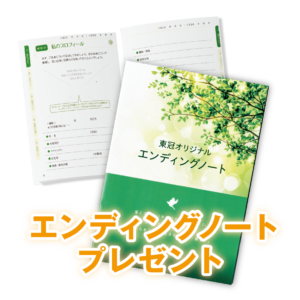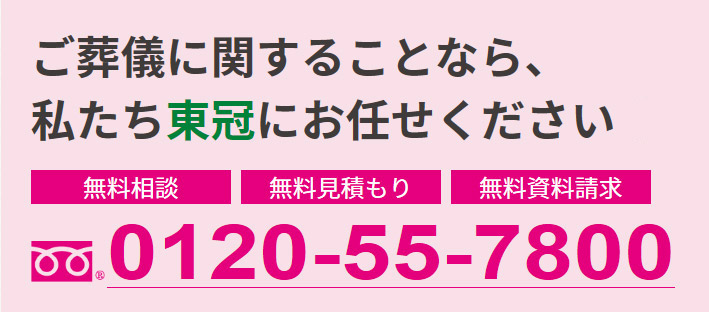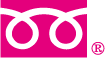従業員のご家族、取引先関係者からの訃報などご不幸があった際に、会社から弔電を送ることがあります。
弔電は、お通夜もしくは葬儀・告別式の開始数時間前までに届くのが望ましく、訃報を聞いたらすぐに手配をしていくのが一般的です。限られた時間の中で対応していくため、基本的なマナーや弔電費用の相場について知っておくと安心ですよね。
今回は、従業員のご親族がお亡くなりになった際に、弔電を会社から送るときの費用相場や、マナーや文例をご紹介します。
弔電を送る前に確認すること
昨今は社会情勢も相まって、ご家族・近親者のみでお通夜や葬儀を行う「家族葬」が増えています。また、会社と個人の関係も昔に比べるとドライになってきており、仕事以外ではできるだけ会社との関わり合いを避けたいと考える方も増えました。
以前から会社からの香典や供物を辞退する方はいましたが、近年では弔電も辞退するケースも珍しくありません。従業員の家族や親族が亡くなったことを知らされたら、弔電の可否を確認してください。
もし、亡くなった知らせと共に「弔電などは辞退します」と申し出られたら、弔電は送らないほうがいいでしょう。また、長年慣例で不幸があったときに弔電を送っていた場合も、「今回からは……」と言われるケースもあるでしょう。ですから、「前回も送ったから」と考えず、その都度確認するのがおすすめです。
費用相場について

3,000円~1万円が一般的です。多くの場合には、2,000円~3,000円の範囲のものか、より印象に残る弔電であれば、5,000円以上のものを選ぶと良いでしょう。
弔電の箱や台紙が厚くなり、高級な印象を与えるものが多くなります。
社内における弔電を送る際の確認事項
社内規定に従って、手配を行います。
まず初めに、葬儀窓口担当者は、葬儀の内容の把握に努めましょう。具体的には、次の項目を確認していきます。
1:いつ、誰がお亡くなりになったのか
社員にとってのご両親・祖父母・ご兄弟など、関係性を把握し、お名前と同時にフリガナも確認します。また合わせて弔電の宛名となる喪主のフルネームも確認しておきます。
2:葬儀日程や場所
お通夜・葬儀の時間・場所をご遺族様から聞き、葬儀社についても確認します。
3:参列の確認
家族葬・一般葬なのか、参列は可能なのかお断りなのかを葬儀社に確認します。把握をしていないと、ご遺族様にご迷惑をお掛けすることになるので、きちんと確認を取りましょう。
4:形式の把握
葬儀が仏式・神式・キリスト式・友人葬などかなど、形式を葬儀社に確認しましょう。
5:駐車場の有無
参列可能な場合に、社内で共有したい情報になります。
上記の1~2については、ご遺族様から、それ以外の項目は葬儀社に問い合わせ、御遺族様へのご負担への配慮をして参りましょう。情報をとりまとめ、社内でどのように対応をするのか、判断を固めていきます。
会社から弔電を送る注意点

1:送り先
弔電は、一般的に通夜や葬儀や告別式が行われる会場・斎場・自宅宛に送ります。火葬ですと、弔電の受け取りが難しいため、自宅宛てにお送りするのが良いでしょう。
2:差出人の情報をしっかりと出す
差出人は、会社名なら略称にせず、必ず正式名称で記載しましょう。連名の場合は、「○一同」などにします。個人名なら高い役職や役員以上の名前で送ります。
個人名を差出人名にする場合には、会社名・部署名・肩書き住所・連絡先を記しておくと丁寧です。
3:忌み言葉に注意
重ね重ね、くれぐれも、いろいろ、皆々様、また、再びといった、重ね言葉など、繰り返しを連想させる言葉はマナー違反になります。
亡くなる、亡くなったなど直接的な表現も避けて、「ご逝去」などと言い換えをしましょう。
4:送るタイミングに注意する
お通夜の日の通夜式の開始前につくように手配するのが望ましいです。弔電はお通夜や葬儀が行われる場所に送るので、会場の確認は必須です。
お通夜を斎場で行う場合は、あまりに早い時間に送ると受取人がいらっしゃらないケースも。開始時刻を併せて確認しておきましょう。
社員の親族がお亡くなりになった際の弔電の文例
お悔やみのお言葉は、簡潔にお伝えするのが望ましいでしょう。以下のような文例の使用がおすすめです。
例)
社内への情報共有
上記の確認事項をまとめ、会社側としての対応を決めた後に、速やかに社員に告知しましょう。告知例をご紹介します。
社員○○の父、○○様が○月○日に○歳でご逝去されました。
通夜:日時
葬儀:日時
場所:(葬儀場の住所・名称)
駐車場:(有無・台数など)
葬儀形式:(仏式・神式・キリスト式・友人葬など)
- 希望参加者はお通夜への参列が可能です
- 葬儀は代表者のみ参列させていただくこととします。
- 香典をご希望の方はお知らせください
- 社内でまとめてお渡しします。
- 香典をご希望の方は、総務の○○までお声がけください。
- ○時までを期限としますので、宜しくお願いいたします。
- 会社から弔電を送る予定です
以上、上記に関してのお問い合わせは、総務の○○までお願いします。
会社の関係者の葬儀に参列する際のマナー
社員の親族がお亡くなりになった場合、お通夜や葬儀に参列することもあります。近年は家族のみでお通夜や葬儀を済ませるケースも増えましたが、地域や会社の規模、亡くなった方の立場によっては大々的な葬儀をすることもあります。
ここでは、会社の関係者の葬儀に参列する際のマナーについてご紹介します。
どのような立場で葬儀に参列するのか
会社の関係者の葬儀に参列するパターンは2種類あります。
一つは、会社の代表者として葬儀に参列する場合、もう一つは故人やその家族と個人的に親しかった場合です。
会社の代表者として参列する場合は、同じく代表になった方とまとまって参加しましょう。香典なども合同で出し、個人ではなく「会社の人間」として振る舞います。
一方、故人やその家族と親しくて葬儀に参加する場合は、会社は関係なく個人として参加します。同社の人と無理に行動を共にする事はありません。
お手伝いを頼まれることもある
社員同士の結びつきが強い会社の場合や、地域によっては社員が通夜や葬儀のお手伝いをすることもあります。お手伝いの内容は、受け付け・案内・接待などがあります。
この中でも受付は、お香典を管理する大切な業務でもあります。何人かで手分けして行うのが一般的ですので、お金から目を離さないようにしましょう。
お通夜のみに参列しても問題ない
会社の代表者として弔問におもむく場合、お通夜だけに参列しても問題ありません。参列する方も、お通夜のみのほうが業務の後に参加できるので、負担が少ないというメリットがあります。この場合、葬儀に参加できないことをお詫びする必要はありません。
服装も、男性ならダークスーツであれば喪服でなくても大丈夫です。ネクタイが赤系統や明るい青系統の場合は、コンビニなどで暗い色のネクタイを調達していきましょう。
社葬に出席する場合のマナー
社葬とは、会社が主体となって行う葬儀のことです。
会社の創業者や会長、社長など知名度の高い方が亡くなった場合や、勤務中に不慮の事故などで社員が亡くなった場合、社葬が行われることがあります。
ここでは、社葬に出席する場合のマナーについて解説します。
出席する社員は故人様と同程度の地位が基本
社葬の出席者は、故人様と同程度の地位の方が基本です。故人様が社長ならば社長が出席しましょう。重要な取引先ほど無礼がないように、近い地位の方が出席するように心がけてください。
社葬特有のマナー
社葬の基本的なマナーは、一般的な葬儀と同様です。特有のマナーとしては、受け付けの際に名刺を差し出します。名刺の右肩に「弔」を入れて、弔意を表します。
代理として出席する場合は、本来出席するはずだった方の名刺も持参し、出席するはずだった方の名刺に「弔」、自分の名刺には「代」を入れてください。名刺は特別なものを用意する必要はありませんが、できるだけシンプルなものを用意しましょう。
社葬の服装
社葬の場合、服装は喪服が一般的です。女性の場合はワンピースやツーピースタイプが動きやすくておすすめです。アクセサリーはパールの一連ネックレスや結婚指輪のみにしましょう。
意外に忘れやすいのが、ネクタイピンです。光沢のあるものをつけてしまうと、黒ネクタイでは目立つので注意しましょう。男性の場合、靴下にも気を配りましょう。
社葬でやってはいけないこと
社葬は葬儀ではありますが、会社の広報の場でもあります。出席する場合は、会社の代表としてきている意識を持ちましょう。
また、社葬ではたくさんの会社関係者が訪れます。取引先が来ることもあれば、ご縁を繋ぎたい会社の代表者が来ることもあるでしょう。つい、名刺交換や商談をしたくなるかもしれません。
しかし、葬儀は故人様を偲ぶ場です。軽い挨拶くらいなら問題ありませんが、会合のように何社とも名刺交換をしたりビジネスの話しをしたりするのはやめましょう。
どうしても、という場合は後日お会いする約束だけしておくといいですね。人の目があることを忘れずにいてください。
まとめ
お葬式が終わるまでの間、遺族は忙しく、お気持ちもとても辛い中で準備や対応に追われています。お悔やみの気持ちを伝えるにしても、マナーを大切にしたいものですよね。
会社で弔電を送る際には、社内で情報の混乱を招かないためにも、きちんと情報を取りまとめることが大切になります。訃報の知らせを受けてからすぐに葬儀に関する確認事項をまとめ、会社としての対応を固めた後に弔電の手配や、香典・参列についてのルールを社内で共有しましょう。
会社から送る弔電は、オフィシャルなメッセージとなります。マナーに沿って弔電を送ることで、お悔やみの気持ちを届けつつ、会社への信頼へ繋がることでしょう。