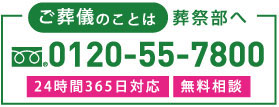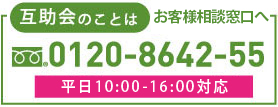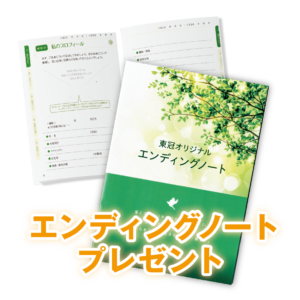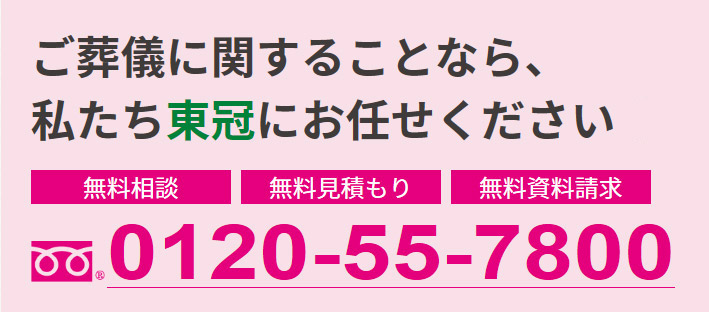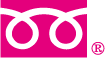「お葬式で故人様への手向けのお品として家族との思い出のあるアイテムや、故人様が生前から大切にされていたものなど、棺の中に入れたい」。実は、棺の中に入れてもよいものもあれば、避けていただきたいものもございます。
この記事では葬儀社が、副葬品としてどのようなアイテムが適しているのかについてご紹介して参ります。
副葬品とその歴史
故人様の棺の中に入れるもの、故人様と一緒に埋葬するものを「副葬品」と呼びます。副葬品の風習は長く、日本では古墳から、世界でも、たとえばエジプトではピラミッドの中から発掘されていますし、中国では秦の始皇帝の兵馬俑も副葬品として有名です。古来の副葬品は、故人の死後にあの世でお金に困らないように納められたり、故人の復活への想いを込めたりしたものだったと言われています。
現代の副葬品の意味は古来のものとは少し違い、旅立つ故人様への手向けの品としての意味合いが強いものとなっています。故人様にまつわる思い出の品や、お写真、お手紙などを納めるご家族様が多いです。
地域によって違う副葬品
地域によっては、副葬品として棺に入れるものが、風習として残っている場合があります。
例えば、昔から三途の川の渡し賃として、六文銭を副葬品にするという風習がありますが、現在では本物の硬貨や紙幣を副葬品にすることはできません。代わりに、木でできたレプリカの六文銭や、紙に印刷した紙幣などのレプリカを副葬品として棺に入れるのが一般的です。
地域に方によっては故人様のへその緒を入れたり、近親者の毛髪や爪を入れることもあるようです。また、故人様が先祖へのお土産としてあの世に持って行く、その土地の産物などを入れる地域もあります。
その他にも様々な風習があり、友引に葬儀をする場合は、その家から二人目の死者が出ないように、ワラ人形を入れることもあります。同様に、同じ家から一年に二度葬儀を出した際にも、三度目の不幸が来ないように、ワラ人形を入れる風習もあります。
地域によって副葬品として入れるものは違ってくるので、風習を知らない方が喪主を務める場合は、年長者に事前に尋ねておきましょう。
なお、副葬品入れるタイミングは、故人様を棺に納めた後になります。火葬場によっては、生花以外の副葬品を禁止しているところもあるようなので、副葬品を入れる場合は、火葬場を選ぶ際に確認をしておきましょう。
副葬品として棺に入れて良いもの

副葬品のアイテムは、一般的に火葬に差しさわりのない「燃えやすいもの」であれば問題ありません。
次のような品々が副葬品として納められています。
お手紙や寄せ書き
ご家族や親族様から、最後に故人様に伝えたい気持ちをしたためたお手紙や寄せ書き、故人様が生前から大切にされていた思い出の手紙をあの世にも持っていけるようにと棺に入れられる場合も多いです。
お花
故人が好んでいた花や育てていた花があれば、ぜひ入れてあげましょう。
お菓子やタバコなどの食品
故人様が生前にお好きだったお菓子などの食品を入れるのも問題ありません。きゅうりのお漬物や好きだった果物類を納められたケースもございました。
ただし、不燃物であるプラスチックや、お酒の瓶などガラスでできているもので包装された食品類は入れられませんので、中身を取り出して納めるなどの工夫が必要になります。
お気に入りのお洋服類
故人様が気に入っていた衣類、着物などは、少ない枚数であれば入れることができます。ハンカチや帽子など服飾小物なども可能ですが、金属やプラスチックの飾りがある場合には外していただく必要がございます。
千羽鶴や朱印帳
どちらも死後の幸福を願う意味を込めて納められるものです。千羽鶴はあまりに量が多いと火葬の妨げになってしまうため、火葬場によっては禁止しているところもございますので、事前にお確かめいただくと良いでしょう。
故人様の趣味にまつわるもの
読書がお好きでしたら、愛読書(ただし分厚いものは入れられません)、試合で着ていたユニフォーム、楽器を演奏されていた肩であれば楽譜など、燃えやすい物を選ぶようにしてください。
また、故人様が可愛がっておられた人形も、燃えやすい材料を使ったものなら、副葬品として棺に入れることができますが、あまり大きなものだと灰が増えるためるため、無理なこともあります。事前に相談しておきましょう。
副葬品として棺に入れてはいけないもの
それでは次に、副葬品として棺に入れられないものについてご紹介して参ります。
一般的には不燃物として分類される、ビニール・プラスチック・ガラス・金属・発泡スチロールのものは入れられません。不燃物でなくても、副葬品として入れない方が良いと言われているものもありますので、確認して行きましょう。
メガネ、結婚指輪、腕時計など
故人様が生前にご愛用されていたメガネや腕時計、結婚指輪 やアクセサリー、その他にも入れ歯なども副葬品として棺の中には入れられません。
金属やガラス類は完全に燃え切らないことも多く、溶けて遺骨を汚してしまう他、火葬炉の故障につながる危険もあるため入れることができません。
火葬後、遺骨とともに骨壺に納めるなどの方法を取ると良いでしょう。
革製品やビニール製の洋服・靴
革やビニールは燃え残りやすく、溶けて遺骨に付着することも。また有毒ガスが出ることもあるため、棺には入れられません。
食べものや飲み物でも缶・プラスチック・ガラス容器に入っているもの
一升びんやビール缶などは燃えないため棺に入れられません。紙パック入りの飲み物は問題ないので、そういったものを探してみましょう。
紙幣・硬貨
硬貨は金属であるため燃やせませんし、また硬貨や紙幣などのお金を燃やすことは法律で禁じられています。しかし、木や紙で作られた副葬品としてのレプリカの硬貨や紙幣を棺に入れる地域もあります。
風習として棺に入れたい場合などは、事前に地元の葬儀社や長老に聞いて、準備をしておきましょう。
分厚い書籍
分厚い本ですと燃えにくく、大量の灰がでることから、灰をかき分けて遺骨を拾わなければならない状態になりかねません。そのため、必要なページのみを切り取るか、分厚いアルバムなら中の写真だけ取り出すなどの工夫をして入れると良いでしょう。
ゴルフクラブや釣竿
燃えない金属や、火葬炉の故障を引き起こすカーボンなどが部品になっているため、棺には入れられません。木製のものもございますが、大きく燃えにくいため火葬場によっては禁止されていることもあります。
水分をたっぷり含んだスイカやメロン
スイカやメロンといった大きさもあり水分も多い食べ物は、燃焼の進行を遅らせてしまう可能性があることから副葬品として認められないケースがあります。どうしても故人様の生前の大好物で入れたい場合には、乾燥させたものを入れたり、写真に撮って入れたりする工夫で対応されることもご検討くださいませ。
スプレー缶やライター、電池などの爆発の可能性があるもの
火葬中突然爆発する可能性があり、副葬品として認められていません。
生きている人が写っている写真
生きている方のお写真を一緒に入れてしまうと「一緒にあの世に連れて行ってしまう」という俗説もあります。故人様がお一人で映られているお写真や、風景の写真などを選択してください。
なお、ペットの写真などは、副葬品として入れても問題ないとされています。
心臓ペースメーカーについて
副葬品とは少し異なりますが、故人様の体内にペースメーカーが入っている場合、医師や看護師等が葬儀社や火葬場の方に直接伝えると、守秘義務違反や個人情報保護法に抵触する可能性があることから、必ずご家族様が申告しましょう。
現在はほとんどの火葬場でペースメーカーを摘出しなくてもそのまま火葬ができますが、火葬炉内でペースメーカーの破裂が起こると、覗き窓付近にいる火葬場の職員に危害がおこる可能性があります。そのため多くの火葬場で、納棺時にペースメーカーをつけているご遺体については職員に申し出るように注意喚起しています。
事前に伝えておくことで、火葬場の職員は、火葬開始からしばらくの間、炉内を見ないようにするため危険が防げます。ペースメーカーの爆発は、炉内にバーナーが点いてから5分~10分でかなり大きな音がするため、火葬に立ち会う方々にも伝えておくことで、心の準備ができます。約15分くらいで安定します。
ペースメーカー装着のご遺体への対応策として、病院でお亡くなりになったときもペースメーカーを摘出せずに、そのままの状態でご家族に引き渡すことが多いようですが、ご家族は、事前に葬儀社や火葬場の職員に故人様がペースメーカーを装着していることを伝えておくことで、トラブルを避けることができます。
ご自宅や入所先でお亡くなりになった場合は、もちろんそのままなので、家族は火葬場の職員や火葬に立ち会う人々に事情を話しておきましょう。
副葬品について、生前にエンディングノートに書いておきましょう
副葬品として棺に入れて良いものと副葬品として棺に入れてはいけないものをお伝えしましたが、ご出棺前の副葬品選びは、「あれもこれも」とつい多くなりがちです。ぜひとも棺に入れてほしい物があれば、生前にエンディングノートに書いておきましょう。また、シンプルに「何も入れてほしくない」なら、そのように書いておくのが、ご遺族様への配慮と言えます。
エンディングノートは、遺言書とは違い法的拘束力はありませんが、希望の葬儀社や葬儀の規模、連絡してほしい親せきや知人の住所や電話番号など、どんなことでも記載できます。
核家族化や高齢化社会が進み、一人世帯が増える中で、スマートに虹の橋を渡るためにも、生前から、なるべく残された人の手を煩わさないようにしておくのも「良い生き方であり、よい死に方」と言えます。
では、「誰に相談すればよいの?」と思われるかもしれませんが、東冠では「東冠オリジナルエンディングノート」を作成しており、ご来館いただいたお客様やお申込みいただいたお客様に無料で差し上げております。
形式や書き方にとらわれることなく、自分の意見や希望を自由に書くことができるので、年齢に関係なくチャレンジすることができます。
まとめ
故人様を送り出す手向けのお品としての副葬品。
様々なルールがありますが、基本的に燃えるもので、爆発などの危険がないもの、有害物質を発することないものであれば、副葬品として認められることがほとんどです。納棺の儀式の流れや副葬品についてご不安な点などございましたら、遠慮なく埼玉の葬儀社「東冠」までご相談ください。
ルールの範囲で悔いなく故人様と丁寧なお別れができるよう、全力でサポートをさせて頂きます。
事前相談のすすめ
この記事では、棺の中に入れる副葬品についてお伝えしましたが、東冠では納得のいくお葬式にしていただくために、葬儀についてのアドバイスや事前相談をおすすめしております。一昔前なら「生きているうちに葬儀についての事前相談なんて縁起でもない」といった風潮でしたが、「近年スマートな終焉」を望む方が増えている傾向にあります。
残念なことではありますが、この世に生を受けた以上、いつか命の終わる時が来ます。その日を心穏やかに迎えるためには、前もって知っておきたいことや確認しておきたいことが誰しもあると思います。東冠では、ご本人様の葬儀に関する事前相談はもちろんのこと、ご家族様のお知りになりたいことについて、どのようなご相談にもていねいにアドバイスをさせていただきます。どうぞご遠慮なくお問い合わせください。
東冠では葬儀についてのアドバイスや、納得のいくお葬式にしていただくために、事前相談をお薦めしておりますので、お気軽にご相談ください。