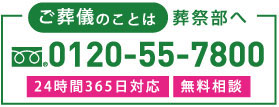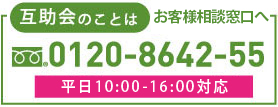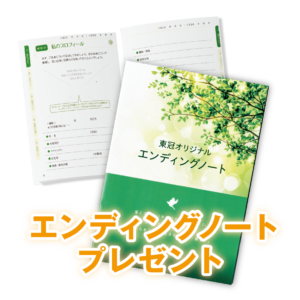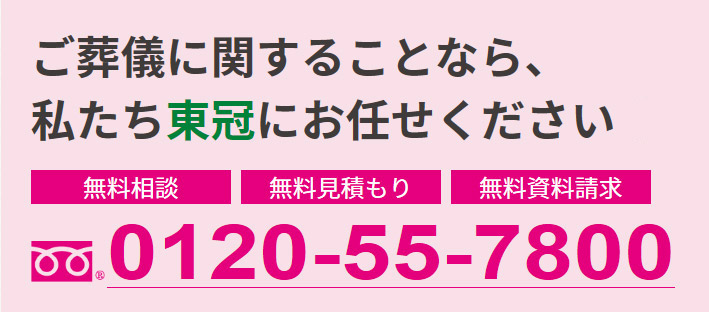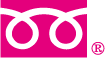「大切な方のお通夜に駆け付けたいけれども、受付に間に合うか分からない」という参列者の方や、「受付を頼まれたものの、どのくらい、受付にいれば良いのだろう?」とご不安の方もいらっしゃることと思います。
この記事では、埼玉エリアの葬儀社「東冠」の頼れるスタッフが、近年のお通夜全体の時間の傾向や、一般的な受付時間をはじめ、受付係・参列者のよくあるご質問についてご紹介して参ります。
受付がもっとも忙しくなる?お通夜について
お通夜とは、葬儀・告別式の前日に行われる儀式のことです。
故人様と親しいご親族様、ご友人様が一同に集まって夜通し最後の夜を偲び、故人様の霊を守り、慰めるという意味がありました。もともとはご家族のみで行われる風習がありましたが、現在では社会的な儀礼として一般客の参列も珍しくありません。
都市部では仕事の都合もあり、葬儀や告別式よりも、お通夜にのみ参列する方が増えています。そのため、葬儀の受付では、葬儀・告別式よりも、お通夜の対応がより忙しくなる傾向があります。
お通夜の受付の適任者は?
受付係は、故人様や喪主と親しいご友人や会社関係者に依頼するケースが多く、2~3人くらいの方に前もってお願いしておきます。また、故人様からみて3親等以上の親族は、遠縁なのでお通夜を仕切る必要もないため、受付係として適任です。
遺族や親族は、通夜式や葬式などの受付をする時間や心の余裕はありませんので、早めに受付係を決めましょう。
受付係を依頼されたが受付係ができない場合の対応について
例えば海外出張中であるとか、病気やケガのため引きうけることができない場合は、その理由を伝え、お悔やみを述べましょう。
受付係の適任者がいない場合は
さまざまな事情で受付係の適任者がいない場合もあります。親族の受付を仕事関係の方にお願いしてもよいのですが、やはり限界があります。そんな場合には受付代行サービスを行っている会社もあるので葬儀社に相談してみましょう。
受付は金銭を扱うことから責任が伴うため、単純なお手伝いではなく、追加料金の場合もありますので確認しておきましょう。なお、小規模な家族葬などでは、特定の受付を置かずに手の空いた遺族が行ないます。
受付係りの仕事の流れについて
- 受付をするための事前準備をする(芳名帳、ご香典を入れる小箱、筆ペン、ご香典を記帳するためのノートやメモ帳など)
- 通夜の受付は、一般的に1時間前から始めます。受付係はそれまでにお手洗いをすませ、身支度を整え、静かに待機します。
弔問客約のあいさつを受ける時は、進行をスムーズにするため、長話は禁物です。 - 芳名帳をご記入いただく。参列者が、次にどうしたらよいか戸惑っている場合には「どうぞ記帳をお済ませください」と促します。
- 香典や弔電、お供え物を受け取る(受け取った香典はひとまとめにしておく)
- 参列者へ会葬礼状・礼品をお渡します。
なお、お預かりしたご香典は、受付係が管理するのか、ご親族様の控室にお持ちするのかを事前に確認しておきましょう。また、お手洗いの場所などを聞かれることもあるため、事前に確認しておきましょう。その他、受付は参列者からお手洗いやクロークの場所を質問される場合があります。
スムーズに案内できるよう、事前に設備の位置を確認しておきましょう。
受付を頼まれた人の服装は?
お通夜の受付を担当する際は、葬儀や告別式と同様にブラックスーツやブラックフォーマルで対応します。男性なら白シャツに黒無地のネクタイ、黒の靴を着用します。派手な時計やブレスレットははずしておきましょう。
女性なら黒のワンピースやアンサンブル、スーツなどで夏でも5分~7分袖が望ましく、ストッキングや靴も黒にします。パールのネックレスをつける場合は、1連のものにします。(不幸ごとには 2連のネックレスは不幸が重なると言ってタブーとなっています)
そもそもお通夜は何時までが一般的?

地域の習わしや参列者の人数にもよるものの、通夜振る舞いを含めますと20~21時が解散時間だと見積もっておきましょう。お通夜の開始時間は、18時~19時が一般的です。家族葬の場合には17時に設定されることもあります。そのため、お通夜の受付を依頼された場合は、通夜式開始時間の1時間半から2時間前までには到着するようにします。できれば、通夜式の前にご遺族様にお悔やみの言葉をかけ、ご焼香をさせていただくと、ご焼香のタイミングを逃さずにすみます。
儀式としてのお通夜は一般的に開式後1時間ほどで閉式となることが多く、その後は、10分程度で通夜振る舞いの会場へ移動することになります。通夜振る舞いまで含めると、お通夜開始から2時間〜参列者の数が多い場合には3時間までが所要時間だと考えておくとよいでしょう。
お通夜の受付係は概ね通夜式には、参列できないと思っておきましょう。特にお通夜の場合は葬儀とは異なり、お通夜が開始されてからも多くの弔問客がお見えになります。受付に誰もいなければ弔問客は戸惑ってしまうため、通夜が終わるまで受付の仕事を行います。
通夜の受付は香典を預かっているという重要な役目も担っているため、気を緩めることができません。その上、お通夜で受付係をした人は、引き続き翌日の葬儀の際にも受付係を任されるケースがほとんどなので、その心づもりをしておく必要もあります。
一般参列の場合は最後まで出席する必要はなく、出席時間の目安は30分~1時間程です。しかし、通夜の受付を任された受付係は最後まで残り、喪主様にお預かりしたご香典やご芳名帳など、お渡ししてから帰るようにしましょう。
お通夜の受付スタート・終了時刻について
受付開始は、通夜式葬儀の規模と参列者の人数を考慮して、通夜式葬儀開始の30分〜1時間前からが一般的です。
儀式としてのお通夜は1時間ほどなので、受付は通夜式お葬儀開始から30分〜1時間までとするケースが多いです。通夜式としたほうがわかりやすいのでは?
受付係の方の焼香はいつまで?

お通夜での受付係の方がお困りになるのが、「どのタイミングで焼香をさせていただくか」という点ではないでしょうか?
結論から言いますと、次の2パターンのご検討がおすすめです。
受付開始よりも前
受付係は葬儀開始の1時間前〜2時間前までに、会場入りすることが一般的です。そのためご遺族様に了承を取られた後に、受付開始よりも前のタイミングで、ご焼香を済ませることができます。
その際には喪主の方に「受付をさせていただく○○です。お先にお焼香をさせていただいてよろしいか」と言葉がけをしましょう。
受付終了後にすぐ
受付終了のタイミングがお通夜開始より30分の場合には、読経の時間が40分〜1時間程度であることを考えても、お焼香はまだ終わっていない可能性が高いです。ですので、受付終了後に後ろのドアから会場へと入り、他の参列者の後に続いてお焼香を行うこともできます。
受付係が悩むこと
受付係は遺族側の立場なので、遺族の代わりに参列者を出迎える際は、失礼がないようにすることが大事です。それでも普段とは違う場所、違う立場で対応しなければならず、さらには葬儀特有の言い回し、タブーも存在します。
ここでは受付係がよく悩む場面の対応について解説します。
こんなときはなんて言う?受付係の対応
参列者のほとんどの方は、受付で「この度はご愁傷様です」「お悔やみ申し上げます」など、お悔やみのお言葉を述べられます。受付係は「本日はお忙しい中、ご参列を賜りありがとうございます」と挨拶をします。
また、雨天の場合などは、「お足元の悪い中、ご参列をいただきありがとうございます」と、ご遺族になりかわってご挨拶をします。ただし、香典や弔電、供物などを受け取った場合は、「お預かりいたします」と、述べます。ご挨拶について厳密な決まりはありませんが、「受付係と言う仕事」と認識し、余計な会話はさし控えましょう。
受付係は、参列者への感謝の気持ちを込めたご挨拶と、遺族の方に必ず届けますとの意味合いを含んだ「お預かりいたします」の一言を添えましょう。つい、「ありがとうございます」と言ってしまいがちですが、受付係が頂いたわけではないので、「お預かりいたします」が常識だと心得ておきましょう。
地声が大きい人や、声のトーンが高い人は、なるべく小声で、声のトーンを下げるように意識して弔問客に対応すると目立ちません。
香典以外の供物を受け取ったときは
お通夜が始まる前には、香典以外の弔電や篭盛といった供物を届けてくれる場合があります。ほとんどは業者が持ってくるはずなので、喪主や葬儀社の方に連絡すれば事足りるでしょう。ただ、その際にも「お預かりいたします」といった基本的な対応は忘れないようにしましょう。
連名でのご香典を受け取った際は香典返しをいくつ渡せばよいか?
会社名義で香典が届いた場合は、会社の経費で準備されているものなので香典返しは不要です。職場からの香典は、一同または有志のどちらかでする場合が多いようです。
一同と記載されている場合は、所属部署の人全員が香典をしているという意味で、有志と記載されている場合は、同僚の何人かが集まって香典をしています。有志での香典は、香典袋の表書きを見て、人数を確認し香典返しを渡します。受付係では分り辛い場合は、葬儀社に相談しましょう。
席を外すときの対応は
少人数で受付をする場合、どうしても受付の席を外してしまう場面もあるでしょう。ただ受付に人がいないと、遅れてきた参列者が戸惑ってしまいます。
香典を一時的に保管する場合もあるため、お金のある場所を無人にしておくのは抵抗があります。前もって喪主や葬儀社と相談しておきましょう。
会計係はどうするのか
受け取った香典をどうするのかも事前に確認しておきましょう。ある程度の規模の葬儀であれば、受付とは別に集計係を設置している場合もあります。
少人数の会場では受付係がそのまま集計することもあります。お金の絡む話でもあるので、誰が責任をもって管理するのか決めておきましょう。
こんなときはどうする?参列者の対応
ここからは参列者の対応を確認していきます。最近は家族葬なども増え、会社関係でのお通夜・葬儀への参列が減ってきました。このため葬儀への参加経験が少ない人も多くいます。
このシチュエーションではどんな対応をすべきなのか、みていきましょう。
自分が親族ではない場合の対応
受付での対応は、自分が故人様の親族かどうかで分かれます。
会社関係や友人関係などの場合は、「このたびはお悔やみ申し上げます」「このたびは誠にご愁傷様でございます」といった言葉で大丈夫です。
「このたびは」といって香典を渡すだけでも十分に伝わります。
自分が親族である場合の対応
受付係の立場はいわば喪主様や親族の代理です。自分も親族である場合は受付係に対してお悔やみの言葉をかけるのは少々おかしなことです。
この場合は、受付係に対して感謝を示すのがスマートなスタイルです。「受付ご苦労様です」といったねぎらいの言葉をかけましょう。香典は「よろしくお願いします」などとシンプルな言葉で渡します。
受付での長話は禁物
受付は香典を渡し、芳名帳に記名し、香典返しを受け取るまで概ね1分程度です。ひとりひとりはすぐに受付できるものの、お通夜の始まる時間帯は多くの参列者で混み合います。
そんな中で受付係が知り合いだからといって立ち話をしたり、長居をしたりすれば他の参列者への迷惑になります。こうした行為はしないようにしましょう。
受け付けに間に合わない場合の対応
「急いで駆け付けたものの、受付時間に間に合わなかった」。受付が終了している場合には、お香典をご遺族に直接お渡しするか、翌日以降に行われるご葬儀・告別式で渡ししましょう。
ご葬儀・告別式に参列できないようであれば、後日ご遺族のお宅に弔問した際に渡すか、郵送すると良いです。
参列する際の注意事項
以前に比べて葬儀も多様化してきました。お通夜の連絡を受けて駆け付ける、だけの時代ではありません。葬儀を開催する側だけでなく、参列する側も考慮すべきことが増えています。
葬儀に参列する際の注意事項についてまとめました。
そもそも参列すべきか
最近は家族葬が増えました。家族葬は一般に少人数で執り行う葬儀で、小規模な会場で開催されます。
このため、仕事関係の方の参列を想定していない場合もあるのです。
葬儀の連絡を受けた場合、まずはどんな葬儀なのか、そもそも自分たちが参列すべきなのか、というところからの確認が必要な時代となりました。
香典辞退かどうかの確認
お通夜や葬儀は開催しても、「香典辞退」「供花辞退」といった特記事項が付されていることもあります。中には香典辞退となっていても、香典を持ってくる参列者もいます。
香典辞退となっていて香典を受け取ると不公平になってしまい、また香典返しも別途用意しなければいけません。香典辞退となっていた場合には、素直に喪主の意向に従いましょう。
職場から直接駆け付ける場合には
仕事などの都合で急きょお通夜に参列しなければいけない場合もあるでしょう。この場合、喪服の準備ができないこともあります。
職場や出先から直接お通夜に参列する場合には、平服でも構わないとされています。その場合でもなるべく黒や紺などの控えめな色合いの服装が望ましいスタイルです。
男性の場合は黒ネクタイならコンビニでも売っていますし、1本職場に買い置きしておいてもよいでしょう。また、男女問わず、アクセサリー類は外すようにしましょう。女性の場合お化粧は薄めに、ナチュラルメイクをこころがけましょう。
まとめ
「受付の時間はいつまで?」をはじめ、主にお通夜での受付係や参列者の質問についてご紹介してきました。
参列するにしても、受付係を引き受けるにしても、事前の準備に時間がないことは共通しています。受付は、弔問客がいらっしゃる30分〜1時間前より受付の開始をし、お通夜の開始から30分〜1時間程度、受付を設けているというケースが一般的ですが、葬儀の規模によっては受付時間の前後が考えられるので、ご遺族様ときちんとご相談の上で受付時間を設定しておくと良いでしょう。
一般の弔問客の方でしたら、お通夜開始から1時間以内には会場に足を運べるよう、段取りされることをおすすめします。