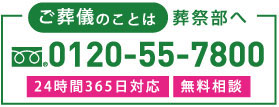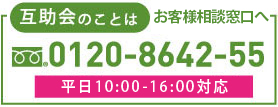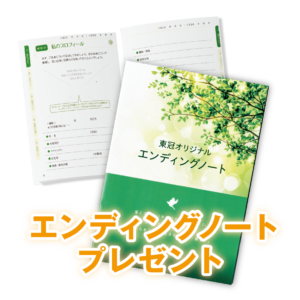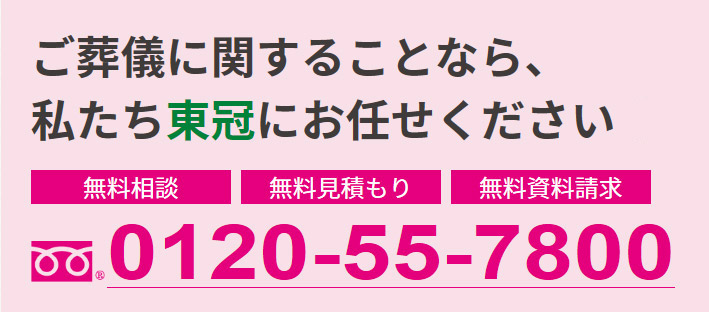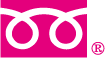お通夜にお葬式と時間のない中で儀式や行事が進んでいきます。お葬儀が終わってひと段落したかと思いきや…、実はお葬儀の後こそ、やるべきことが山積みなのです。
さらに、手続き期間が14日以内など短いものも多いため、「知らなかった」という事態にならないためにも、必要な手続きを知っておく必要があります。
今回は葬儀後に必要な各種手続きとその流れについてのご紹介です。
死亡から14日以内に行うべき手続き

葬儀が終わった後も遺族の方には気の休まる暇がありません。行政への手続きなど、時間的な締め切りがあるものが目白押しです。これらの多くは、手続きを怠ってしまうと、もらえるものがもらえなかったり、罰則などが伴ったりするものもあります。
お通夜、葬儀が終わってひと休みする前にすべき手続きをみていきましょう。
年金受給権者死亡届
提出先は市区町村の窓口もしくは、年金事務所のどちらかになります。厚生年金の場合は受給者が亡くなってから10日以内に住所地の市町村役場での手続きが必要です。国民年金を受け取っていた場合は受給者が亡くなってから14日以内に年金事務所などでの手続きとなります。
生前加入していた年金の種類が分からない場合は、年金事務所に確認しましょう。
※日本年金機構に個人番号(マイナンバー)の記録があれば、年金受給権者死亡届の提出は必要です。
健康保険証の返却
健康保険証はそれを発行している保険者に返却します。
国民健康保険の場合は市町村、故人様がサラリーマンなどの現役だった場合で、健康保険に加入していた場合には勤務していた会社、現役の公務員だった場合は共済組合と返却先が異なります。特にサラリーマンが対象となる健康保険は死亡後5日以内に資格喪失届を提出しなければなりません。
健康保険は死亡の翌日から本人分は使用できなくなります。扶養に入っていた家族は、他の家族の扶養に入らない場合には国民健康保険に加入することになります。
パスポート・運転免許証などの返却
パスポートは旅券事務所やパスポートセンターに返却します。実は旅券法に名義人、つまり本人が死亡した際にパスポートはその効力を失うと明記されています。本人の死亡時にパスポートはその効力がなくなるのです。
運転免許証もパスポートと返納手続きはほぼ同様です。運転免許証は警察や運転免許センターに返納します。
パスポートや免許証は身分を示す重要な書類なので、盗難などによって不正な使用に使われる可能性もあり、早めの返納がおススメです。
公共料金・契約サービスの名義変更・解約
携帯・公共料金・クレジットカード・不動産などの解約・名義変更も速やかに行いましょう。携帯料金や公共料金は故人様が一人暮らしであれば解約手続きです。同居していた場合は名義変更の場合もあります。
こうした料金は本人が亡くなっていても発生してしまう料金ですので早めの手続きをしましょう。
遺言書の検認
遺言書の有無によってその後の相続の方向性が決定されるため、遺言書がある場合すみやかに家庭裁判所に提出して検認が必要です。開封してしまうと法律違反になりますのであせらずに手続きをしましょう。
遺言や相続については専門的な知識が必要なうえ、親族同士が利害関係者になりうるため、税理士や弁護士などの専門家のアドバイスを受けることをおススメします。
介護保険資格喪失届
故人様が介護保険の被保険者(65歳以上または、40歳以上65歳未満で要介護認定を受けていた)であった場合、14日以内に、住民票がある市区町村の福祉課への届け出が必要です。
この際、介護保険証の返却が必要なので、確保したうえで役所にいくようにしましょう。
国民健康保険・後期高齢者医療制度脱退
国民健康保険や後期高齢者医療制度(75歳以上の方)に加入していた方が死亡した場合は、14日以内の各脱退手続きが必要です。市区町村の国民健康保険窓口で手続きを進めてください。
亡くなった人が会社員等であった場合は、健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届の届け出が必要ですが、会社の方で行うケースが多いので会社に確認するようにします。
住民票の抹消届
故人様が亡くなってから14日以内に市区町村の戸籍・住民登録窓口で手続きを進めます。この抹消届は死亡届の提出により自動的に処理されるケースが多いため、遺族の方が特別な手続きがない場合もあります。こうした省力化も手続き簡略化の一環なのです。
世帯主の変更届
亡くなった故人様が世帯主であった場合には、14日以内に市町村の役場に提出します。世帯員が1人になるケースでは、世帯主の変更届を提出が不要な場合もあるので市町村に要確認です。
住民票の抹消届と同時に行えるように様式が整備されている市町村もあるため、同時に行うとよいでしょう。
死亡から1ヶ月〜10ヶ月以内に行うべき手続き

雇用保険受給資格者証の返還
故人が雇用保険を受給していた場合、死亡から1ヶ月以内に受給していたハローワークに「雇用保険受給資格者証」を返却する必要があります。
この雇用保険受給資格者証は失業保険の受給資格があることを証明するものです。死亡診断書や住民票とともに受給者証を返却します。
生命保険の保険金請求
保険金請求ができる場合には保険会社へ連絡をして請求手続きを行います。保険会社からは主に「保険証券番号」「亡くなった人の氏名」「亡くなった日」「死亡原因」「保険金受取人の氏名」「保険金受取人の連絡先」を聞かれます。
これらが記載してあるのが保険証券で、保険金を請求する際には保険証券を手元に置いておきましょう。
故人様の所得税の申告手続き
相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に行います。これは確定申告に準ずるものとして、その名称は「準確定申告」です。ただし公的年金等による収入が400万円以下で、他の所得も20万円以下の場合、確定申告は必要ありません。
この準確定申告で申告される内容は、故人様の財産とみなされます。相続財産と一部ともみなされるため、準確定申告は相続手続きと同時並行で行うのがよいでしょう。
団体信用生命保険金の請求手続き
故人様が住宅ローンを借りて団体信用生命保険に加入していれば、その請求手続きが必要です。団体信用生命保険は、被保険者が死亡した場合に全国信用保証協会が住宅ローンの残債を肩代わりしてくれる制度のこと。
この請求手続きは死亡後2カ月以内に行う必要があります。住宅ローンを借りている金融機関が窓口ですので忘れずに相談しましょう。
相続関連の手続き
自動車所有権の移転
相続から15日以内に陸運局やその支局に届け出をします。陸運局やその支局は普段は馴染みの薄い場所なのでどこにあるのか、調べることも大事です。
そのまま放置しておくと、売却ができないなどの弊害が発生します。
相続放棄をする場合
何等かの理由があり、相続を辞退する場合、相続開始後3ヶ月以内に家庭裁判所にて手続きを進めます。相続放棄をするには、「相続放棄申述書」を作成し提出することが必要です。それだけでなく、裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届いて初めて相続放棄が実現します。
受理されるあいだにも裁判所から質問書が届いて、それに回答するなどのやり取りも必要です。
相続税の申告
相続したことで相続税がかかる場合には、相続から10ヵ月以内に地方法務局にて相続税の申告をしなければなりません。さらに、相続税の納税や、不動産の名義変更なども同時に10ヵ月以内に済ませる必要があります。
相続税はかつてごく一部の人が対象でしたが、法改正の結果、相続税の対象者が増えました。この相続税の申告はもちろん自分で行うこともできますが、制度や計算方法が複雑なため、税理士に依頼することがオススメです。
この他2〜5年以内に行うべき手続きも

以下の補助金や給付金は、申請することで払い戻しや金銭支給を受け取ることが可能です。
特に国民年金は死亡一時金や遺族基礎年金など複数の手続きが必要です。死亡一時基金は生計を同じくしていた遺族の方が受け取ることができ、故人様の加入期間にもよりますが、加入期間が420カ月以上なら32万円を受け取れます。遺族基礎年金も遺族の方が受け取れる年金のひとつで、家族構成によってはこの遺族基礎年金が主要な収入になることもある年金です。
国民健康保険には葬祭費給付金制度があり、故人様が国民健康保険に加入されていた場合は葬祭費を受け取れます。なお故人様が亡くなった時に加入していたのが、健康保険組合や協会けんぽだった場合は埋葬料となります。埋葬料は死亡後2年が申請期限です。
高額医療費の請求は死亡後2年以内に行うことができ、高額医療費の申請書、高額医療費払い戻しの案内書、健康保険証で申請することができます。
公共料金やクレジットカード、加入中のサービスに係る解約などもできるだけ早く行うことが好ましいです。
婚姻前の名字に戻す「復氏届」、姻族関係を終了したい場合には「姻族関係終了届」の提出なども希望をすれば行うことができます。
まとめ
ここでは、葬儀後の事務手続きについて一通りのものをご紹介して参りました。これらの中には期限が限られている手続き等もあり、葬儀と同時並行または葬儀後すぐに行わなければならないものもあります。相続のように手続きが長期間にわたるものもあり、なかなか故人様と向き合う時間も取れないかもしれません。
葬儀後は辛いお気持ちを抱えてもなお、するべきことが沢山あり、ご遺族様は慌ただしいかと思います。葬儀後に行うことをリスト化し優先順位を付けながら、落ち着いて1つずつ整理をしてみてください。
本日もお付き合い下さりありがとうございました。埼玉の葬儀社「東冠」では、他にも葬儀に関連するお役立ち情報をご紹介していますので、お役立てくださいませ。